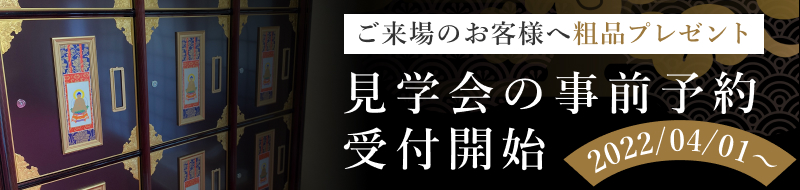大牟田で葬儀に関するご相談は、大牟田市三池にある禅寺【金井寺】へ。
境内には「桜姫伝説」の御堂があり、集合型のお墓「納骨墓」やペット霊園もございます。葬儀のご相談から日常生活に生じるお悩みまで、どんなことでもお聞かせください。
大牟田の金井寺は黄檗宗(おうばくしゅう)という宗派のお寺です。
黄檗宗とは禅宗の流れをくむ一派で、葬儀・永代供養・納骨・ペット霊園といった地域の仏事をご相談いただけます。
宗派にとらわれすぎることなく、地域の人たちのお悩みを軽くできる場所、気軽におしゃべりに来ていただける場所として身近にあるお寺です。
葬儀といった仏事の際はもちろん、普段から気兼ねなくお立ち寄りください。
大牟田の金井寺について 葬儀・永代供養・納骨から日常生活のお悩みまで気軽にご相談いただけるお寺
黄檗宗(おうばくしゅう) 金井寺(きんせいじ)は、福岡県大牟田市三池にある禅寺。境内には「桜姫伝説」のある由緒正しき寺院です。
JR鹿児島本線「銀水駅」から徒歩18分という場所にあり、静かで風情も豊かな場所で檀家様だけではなく、知っていただいたすべての方々に親しみと共感を得るお寺作りに取り組んでいます。
仏事のご相談から、日常生活に生じるお悩み、あるいはおしゃべりをしたいという理由でも結構です。どうぞ、気軽にお立ち寄りください。
住職 國崎 泰正
「納骨墓(のうこつぼ)」とは、屋外に設置された従来のお墓のスタイルにもっとも近いマンションのような集合型のお墓...続きを読む >
大牟田で葬儀のことなら
大牟田で葬儀を行う寺をお探しなら【金井寺】にお任せください。
大牟田市三池にある【金井寺】は、久留米市・福岡市・みやま市・柳川市など、福岡の幅広いエリアへ出向いたします。一件一件丁寧に執り行いますので、大切な方の最期のお別れには是非【金井寺】へご依頼ください。
お墓をどのようにしたらよいかわからない、葬儀の相場がどのくらいか知りたいなど、どんなことでもご相談を承ります。跡継ぎがいなく、今後のお墓の管理が心配という方には、永代供養墓をご用意しております。詳しい内容、費用について随時お問い合わせを承りますので、お気軽にご連絡ください。